昨晩、麻雀ゲームをやっていたら知らない役満で上がられた、、、
初めて聴いた役満役、、、、
ゴールデンゲートブリッジ、、、、なんじゃそれ、、、
「ゴールデンゲートブリッジ」は、麻雀のローカル役の一つで、役満とされています。
成立条件
同じ種類の数牌で「123・345・567・789」の4つの順子を揃え、それに加えて雀頭が必要です。
特徴
- アメリカ由来の役: サンフランシスコにある有名な橋「ゴールデンゲートブリッジ」の形に由来すると言われています。1から9までの牌が揃う形が、橋のアーチのように見えるためこの名前がついたようです。
- ローカル役: 日本の標準的な麻雀ルールでは採用されていません。主に一部の地域や仲間内のルールで採用されています。特に、関西地方の一部で人気があるようです。
- 役満: 成立が難しい分、アガると高得点が期待できます。ダブル役満とするルールも存在するようです。
- 清一色との複合: 一部のルールでは、ゴールデンゲートブリッジは清一色(同じ種類の牌のみで手を作る役)であることが条件とされる場合があります。さらに、雀頭が「5」の牌である必要があるという説もあります。
- 中国麻雀との関連: 中国麻雀の役である「一色四歩高(イーソー・スーポートー)」に相当するとされていますが、1ずつずれた形を認めるかどうかはルールによって異なるようです。
もし、あなたがプレイする麻雀でこの役が採用されているかを確認すると良いでしょう。
ローカル役みたいですな
そんなもんわからんがな、、、
ほかにもあるんかな、、、ローカル役、、、
麻雀のローカル役、面白いですよね!地域によって様々な役があって、奥深さを感じます。イラスト付きで、いくつか代表的なローカル役をご紹介しますね。
代表的なローカル役
1. 頭跳ね (あたまはね)
- 成立条件: 他の人がロンと言った牌と同じ牌で自分の待ちができていて、その牌でツモアガリした場合に成立します。
- 翻数: 1翻
- 特徴: 他の人がロンアガリした牌を、自分がツモるという珍しいケースで成立する役です。
- イラスト:
捨て牌の中に🀐があり、自分の手牌に🀐🀑待ちがあり、🀐をツモる
2. 一色二順 (いっしょくにじゅん)
- 成立条件: 同じ種類の牌(萬子、筒子、索子)で2種類以上の順子(シュンツ)を作り、それが2巡目以内に完成した場合に成立します。
- 翻数: 2翻
- 特徴: スピーディーな手作りが求められる役です。
- イラスト:
手牌に🀇🀈🀉と🀈🀉🀊があり、どちらも2巡目以内に完成している
3. 三連刻 (さんれんこ)
- 成立条件: 同じ種類の牌で、数字が連続する3つ以上の刻子(コーツ)を揃えることで成立します。
- 翻数: 2翻
- 特徴: 比較的狙いにくいですが、完成した時の喜びは大きいです。
- イラスト:
手牌に🀐🀐🀐、🀑🀑🀑、🀒🀒🀒がある
4. 四連刻 (スーレンコ)
- 成立条件: 同じ種類の牌で、数字が連続する4つの刻子を揃えることで成立します。
- 翻数: 役満
- 特徴: 非常に難易度が高く、ローカル役の中でも特に高得点が期待できます。
- イラスト:
手牌に🀐🀐🀐、🀑🀑🀑、🀒🀒🀒、🀓🀓🀓がある
5. 大車輪 (ダイシャリン)
- 成立条件: 筒子(ピンズ)の2から8までの連番の牌で、七対子(チートイツ)の形にすると成立します。
- 翻数: 役満
- 特徴: 形が非常に特徴的で、狙うと面白い役です。
- イラスト:
手牌に🀑🀑、🀒🀒、🀓🀓、🀔🀔、🀕🀕、🀖🀖、🀗🀗がある
6. 紅孔雀 (ホンクジャク)
- 成立条件: 字牌の「白」「發」「中」のみで七対子の形にすると成立します。
- 翻数: 役満
- 特徴: 字牌のみを使う美しい役です。
7. 石の上にも三年 (いしのうえにもさんねん)
- 成立条件: 同じ牌を3年以上持ち続けてアガると成立する…というのは冗談です!実際には、特定の場所で3年以上続けて麻雀を打っているメンバーで成立するローカルルールなどがあります。
- 翻数: (ルールによります)
- 特徴: ユニークな名前の役で、コミュニティの絆を表すような意味合いがあるかもしれませんね。
注意点
ローカル役は、地域や雀荘、メンバーによって採用されているかどうかが異なります。遊ぶ前に、どのようなローカル役があるかを確認することが大切です。
他にもたくさんのローカル役がありますが、今回は代表的なものをいくつかご紹介しました。これらの役を覚えておくと、麻雀がさらに楽しくなるかもしれませんね!何か他に知りたいローカル役はありますか?
実際に作っている役でもあるけど有効になっていない場合がある気がする、、
所詮ゲーム内でやっていることだから、ひとまず上がる事ができれば何でもよいか、、、
とおじさんは思っています、、、勝てば官軍、、、
行ってきました、、、池袋、、、

聖地巡礼、、、、IWGP、、、で話題の
いけふくろう
実際に見てきましたが結構大きい、、、

サンシャイン60です、、、
小学生の頃ぶりですか、、、
約40年ぶりだと思います、、、、
池袋なんて早々行きませんからね、、、
せいぜい新宿止まり、、、行っても東京ビックサイトとか、、、ですか、、、
改めて上を見渡すと背の高いビルばかり

人が一杯、、、よくビルとか人の重みで潰れないな~って思うくらい人がいっぱい、、、
考えが小学生並みですが、、、不思議じゃないですか、、、
疑問をぶつけてみた、、、、
高層ビルが倒れたり潰れたりしないのには、いくつかの重要な理由があります。
1. 強固な構造設計:
- 強靭な骨組み: 高層ビルは、鉄骨や鉄筋コンクリートといった非常に強度の高い材料で骨組みが作られています。これらの材料は、建物の重さをしっかりと支えるだけでなく、地震や強風などの外部からの力にも耐えることができます。
- 荷重の分散: 建物の重さは、柱や梁といった構造部材を通じて、基礎へと均等に分散されるように設計されています。これにより、一点に過度な負荷がかかるのを防ぎます。
- 柔軟性: 高層ビルは、ある程度の柔軟性を持つように設計されています。地震や強風の際には、建物全体がわずかに揺れることで、エネルギーを吸収し、倒壊を防ぎます。まるで、しなやかな木の枝が強風に耐えるようなイメージです。
2. 地震対策:
- 免震・制震技術: 近年の高層ビルには、地震の揺れを吸収したり、建物の揺れを抑えるための様々な技術が導入されています。
- 免震構造: 建物の基礎部分に特殊な装置を設置し、地面の揺れが建物に直接伝わるのを防ぎます。
- 制震構造: 建物内部にダンパーと呼ばれる装置を設置し、地震のエネルギーを吸収して揺れを小さくします。
- 粘り強い材料: 地震の揺れに耐えるため、変形しにくく、粘り強い材料が使用されています。
3. 風対策:
- 空気力学に基づいた設計: 高層ビルの形状は、風の抵抗を最小限に抑えるように工夫されています。角を丸くしたり、途中でくびれを設けたりするなどの工夫が見られます。
- 制振装置: 強風による建物の揺れを抑えるために、屋上などに制振装置が設置されることがあります。
4. 厳しい建築基準:
- 各国や地域ごとに、建物の安全性に関する厳しい建築基準が定められています。高層ビルを建設する際には、これらの基準をクリアすることが義務付けられています。
例えるなら:
高層ビルは、人間の骨格のように強靭な骨組みを持ち、関節のように柔軟性も備えています。そして、地震や風といった外部からの力に対しては、まるで鍛えられた筋肉のように、しっかりと耐えることができるように設計されているのです。また、建築基準という厳しいルールによって、その安全性がしっかりと守られています。
このように、様々な技術と工夫によって、高層ビルは多くの人が入っても倒れたり潰れたりすることなく、安全に利用できるのです。
それでも不思議、、、、

ホントビルばっかり、、、田舎モン丸出しでした、、、
おじさんは田舎モンでした、、
最後まで御覧いただきありがとうございます
本日もご愛読ありがとうございました



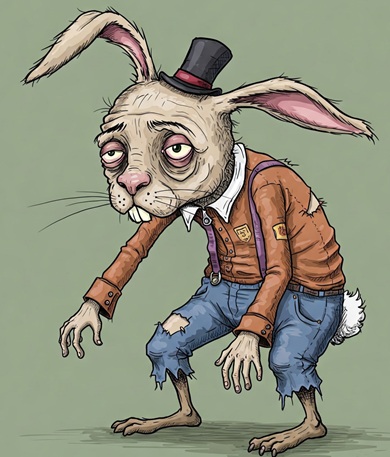


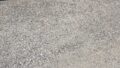
コメント